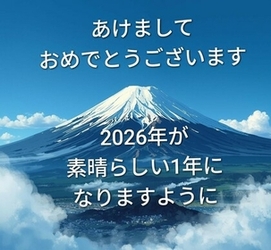- ホーム
- 【コラム】50代からの「不動産」と「お金」
- 住宅ローン不安
- 【住宅ローンが不安】いくら借りられるの?
【住宅ローンが不安】いくら借りられるの?
2018/09/24無理な金額の住宅ローンを借りるつもりはないけれど、そもそも自分たちはいくらまで貸してもらえるのだろう?とマイホームを考え始めたら気になるかもしれません。
もちろん最終的には金融機関の審査を受けなければ結論は出ません。
まだ借りるかどうか分からないのに金融機関に相談には行きづらいという時には次のように計算してみると良いです。
住宅ローンの借入可能額を導きだすのに知っておいた方が良いポイントがあります。
住宅ローン借入可能額算出3つのポイント
- 審査金利
- 返済負担率
- 完済年齢
審査金利とは?
もし変動金利0.7%と宣伝しているA銀行で借りようと考えていた場合、審査に申込みをした場合、0.7%で返済していける人かどうかという視点では審査しません。
なぜなら返済期間中、ずっと0.7%とは限らないからです。金利が上昇することも考えられます。銀行は金利が上昇しても返済できる人かどうかをチェックします。
そのため審査金利と言う別の金利を使って審査しています。
審査金利は銀行毎に違いますが、10年固定金利の店頭金利(優遇前の金利)を採用しているケースが多いようです。2018年8月時点だと2.7%前後です。
銀行毎に違うと書きましたが、地銀や信金の中には実際に借りる金利で審査する銀行もあります。例えば変動金利を選択するのなら0.7%で審査をしてくれるということです。
同じ人に対してA銀行は2.7%、B銀行は0.7%で審査をするという現象が起きます。
これがどういう違いを生じさせるかというと次に触れる返済負担率とも関係しますが、同じ収入でも審査する銀行によって借りられる金額に差が出るという現象が起きます。だいたい同じくらいの金額と言うレベルではなく数百万円から1千万円単位で変わります。
後程、具体例を示します。
返済負担率
返済負担率は申込人の収入に対する返済額の比率のことです。これも金融機関が年収●●万円までの人は返済負担率30%までとか決めています。
ホームページには載せていないケースも多いですが、フラット35は明示しています。
返済負担率(フラット35の場合)
年収400万円以下 30%
年収400万円超 35%
例えば
年収500万円の場合
500万円 × 35% = 175万円(年間)
175万円 ÷ 12か月 = 約14万円
年収500万円の場合、毎月の返済額が約14万円までは貸せる範囲と見なされます。
では、この14万円までは返済可能と見なしている場合、銀行毎に借入可能額がどのように変わるのかを見ていきます。
1で触れたように審査金利は銀行によって違いますので、次のような前提で計算します。
A銀行 審査金利 2.7% 返済負担率 35%以内
B銀行 審査金利 0.7% 返済負担率 35%以内
1000万円あたりの毎月の返済額(35年返済)
7% 36,830円
7% 26,852円
年収500万円の場合、毎月14万円まで返済可能と計算されているので
A銀行 140,000円 ÷ 36,830円 = 3.8 (3800万円)
B銀行 140,000円 ÷ 26,852円 = 5.2 (5200万円)
A銀行は3800万円、B銀行は5200万円まで貸せる可能性があると計算できます。
もし既に自動車ローンなどの借り入れがあれば、その返済額をこの例なら14万円から差し引いて計算します。
毎月の返済額が3万円の自動車ローンを借りている場合
14万円 − 3万円 = 11万円
11万円が住宅ローンの審査上での返済可能額となります。
完済年齢
住宅ローンは最長35年間借りられます。
ただ全員が35年間で借りられるわけではありません。
多くの銀行で住宅ローン完済時の年齢を80歳なるまでと設定して、それまでに完済できる期間で最長35年間という考え方をしています。
逆にいうと最長35年間を借りようとすると45歳になるまでに借入をしないと35年間は借りられません。
年齢的に購入時期が該当する場合は年数に気を付けなければいけません。
ただ多くの会社員が60歳から65歳の間で定年退職を迎えます。そこから80歳になるまでの15年近くの返済をしていくことを考えると銀行の審査も厳しくなることが想像できます。
まとめ
ここまでは自分で計算をする方法に触れてきましたが、最近では自分の年収を入力すれば簡単に借入可能額が出せるサイトもたくさんあります。
そういったサイトを利用してみてもよいでしょう。
-
 空き家になった実家の活用ステップ
~あなたの実家をどうするか問題~
はじめに50歳代になると段々と現実的になってくる問題のひとつに「空き家になった実家」の問題があります。戦後、何
空き家になった実家の活用ステップ
~あなたの実家をどうするか問題~
はじめに50歳代になると段々と現実的になってくる問題のひとつに「空き家になった実家」の問題があります。戦後、何
-
 50代からの住み替えで考えておきたい3つの視点
はじめに:住み替えを考える50歳代夫婦の背景50歳代以降の夫婦は、子どもの独立や退職を見すえて、一戸建てから駅
50代からの住み替えで考えておきたい3つの視点
はじめに:住み替えを考える50歳代夫婦の背景50歳代以降の夫婦は、子どもの独立や退職を見すえて、一戸建てから駅
-
 実家が空き家になるなら最低限これはやろう
はじめに:実家を相続すること実家を相続することは、不動産という資産を相続するという観点からは、一見喜ばしいかも
実家が空き家になるなら最低限これはやろう
はじめに:実家を相続すること実家を相続することは、不動産という資産を相続するという観点からは、一見喜ばしいかも
-
 「親の終活」のはじめの一歩
「終活」という言葉は、週刊誌で老い支度の特集をした際に作られた造語です。今やすっかり市民権を得ているようにも感
「親の終活」のはじめの一歩
「終活」という言葉は、週刊誌で老い支度の特集をした際に作られた造語です。今やすっかり市民権を得ているようにも感
-
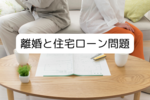 サザエとマスオが離婚したらどうなる住宅ローン
1. 住宅ローンが離婚後の生活に与える影響熟年離婚という言葉もありますが、子供も独立して、いよいよ夫婦だけの生
サザエとマスオが離婚したらどうなる住宅ローン
1. 住宅ローンが離婚後の生活に与える影響熟年離婚という言葉もありますが、子供も独立して、いよいよ夫婦だけの生
ご相談予約・お問い合わせはこちら

ご予約・お問い合わせは下記のフォームにて受け付けております。
◆ 船橋事務所|千葉県船橋市上山町1-236-1(船橋相談スペースの住所は違うところです)